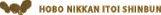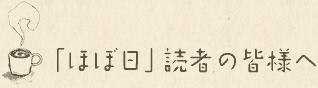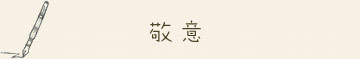| 去年の暮れ、 松井秀喜選手が突然、引退を発表した。 スポーツ選手なら、遅かれ早かれ 誰でも経験する日に違いない。 すでに松井選手は38歳。 ここ数年のコンディション、 そして次の球団が決まらない状況を考えると 引退は時間の問題だったと言ってもいい。 でもそのことが、年が明けても 自分の中で折り合いがつけられないでいる。 彼が偉大な選手だったということもあるだろう。 だが、それだけではないような気がした。 考えているうち、ひとつの答えにたどり着いた。 それは自分にとって かけがえのない日々の記憶の中心に 松井選手がいるということだった。 私は、2004年3月に ニューヨークに赴任した。 前任者からの引き継ぎを終え、 少し仕事に慣れてきたのを見計らって 大リーグ担当の笹田幸嗣記者に ヤンキースタジアムに連れて行ってもらった。 といっても観客席ではない。 ロッカールームに生まれて初めて入ったのだ。 日焼けして いつも笑顔を絶やさない笹田記者は 大リーグに魅せられて アメリカにやってきた。 いや、大リーグに挑戦する日本人に 自分の夢を重ねたというほうがいいかもしれない。 1995年、野茂英雄投手が アメリカ西海岸に舞台を移すと あっさり会社を辞めて日本を飛び出した。  「こっちでは記者が 選手たちのロッカールームに入れるんですよ」 笹田記者が慣れた様子で、球場内を先導する。 日本の球場ではそれが叶わないことすら 私は知らなかったのだが、 入ってみて、そのオープンさに驚いた。 ヤンキースの名だたる選手が 目の前で、すっぱだかで着替えているのだ。 入れない日本のほうが 自然なのではないかとも思ったが、 取材のルールができるまでには 選手とメディアの間で 押したり引いたりという 長いやりとりが繰り返されてきたのだろう。 ロッカールームで紹介された松井選手は 聞いていた通りの礼儀正しさで こちらが恐縮するほどだった。 どういうタイミングだったか 上半身裸で座っていたのだが、 鍛え抜かれた筋肉に触らせてもらうと その柔らかさに思わず唸った。 しなやかなバッティングホームの 秘密の一端を目撃したような気がして 妙にはしゃいだ気分になったものだ。 それから球場で、試合の後に 松井選手が会見する場に なんどか立ち合ったことがある。 ご存じのとおり 松井選手は、活躍した試合だけでなく どんなに調子が悪い時でも カメラの前に立ち続けてきた。 記者たちからすると こんなありがたい存在はない。 取材に来れば、必ず映像と 本人の声が取れるのだ。 それに加えて人柄なのだろう、 松井選手と記者たちの間には 打ちとけた雰囲気が醸成されていた。 それとは対照的な雰囲気を感じたことがある。 イチロー選手だ。 やはりロッカールームでの出来事だ。 試合を終えたイチロー選手が シャワーを浴びて落ち着くタイミングを 記者たちが遠巻きにうかがっている。 イチロー選手が合図するかのように タオルを首にかけて椅子に座ると 記者たちがぞろぞろと周りを囲んだ。 記者たちがこわごわ、質問を発し、 イチロー選手がいつものように 選び抜いた言葉を返す。 私が見ていたそのやりとりでは つまらない質問ととるや イチロー選手は答えようとしなかった。 自分がぎりぎりで闘っているのだから 記者にもプロフェッショナルを求め、 それを持ちえる記者は評価する。 サッカーの中田英寿選手の スタイルにも通じるように思えた。 ロッカールームでは それぞれの選手の流儀も垣間見えるのだ。  ニューヨークで暮らした4年間で ヤンキースタジアムに何度、 足を運んだだろうか。 ひとつのシーズンに だいたい7回から8回ほど行ったので おそらく30回近くは スタジアムに身を置いたことになる。 初めて行ったときから その独特の雰囲気が ひどく心地よかったのを覚えている。 うまく言えないが 球場全体に“敬意”が溢れているのだ。 それがヤンキースタジアム独特のものなのか それともアメリカの他の球場にも 言えることなのかわからない。 もちろん日本でも プロ野球の選手は尊敬されているとは思う。 だがヤンキースタジアムに入ると 観客たちが選手たちに敬意を払っているのが もうそこに身を置くだけでわかるのだ。 アメリカ社会は、競争に満ちているからか どんな分野であれ、 がんばって成功した人には きちんと敬意を払う社会のように思う。 どこかで同質であることを求められ 出る杭は打たれ、嫉妬の対象になりやすい 日本の社会と違って 皆と同じであることを嫌い、 個性を重んじる国の有りようから考えると 自然な成り行きなのかもしれない。 さらにベースボール発祥の国、 ファンたちは野球が大好きなんだと思う。 拍手は活躍した選手だけのものではない。 走者を進めるために犠牲になる、といった 地味な仕事をきちんとこなした打者にも 観客は惜しみない拍手を送り、 たとえ打たれてベンチに下げられた投手でも いいピッチングをしていれば 時にスタンディングオベーションで迎える。 どこか神聖な佇まいのその場所で 松井選手は間違いなく愛され、 これ以上ないほどの敬意を払われていた。 松井選手の背番号55をつけた ユニフォームを着たファンが 観客席のあちこちにいる。 父とまだ小学生くらいの息子が そろって55番のユニフォームを着ている 光景を目にするのも珍しくなかった。 バッターボックスに立つと 「マツイ、マツイ」の大合唱が響いた。 そんなとき、同じ日本人として どれだけ誇らしく思ったことか。 チームのために黙々とプレーする姿に ニューヨーカーは魅せられていったのだろう。 ヤンキースの4番をも任された 松井選手への熱い思いは 球場の周りでマイクを向けるとすぐに拾えたし、 55番のユニフォームの売り上げが チームでいつも 3本の指に入っていたほどの人気だった。  2006年の出来事は忘れない。 レフトの守備についていた松井選手は 浅いフライを取ろうと滑り込み 左手首を骨折した。 翌日、手術を終えた松井選手は声明を発表、 その内容が全米を驚かせた。 文面の中に 「アイ、フィール、ベリー、ソーリー」という 深い謝罪の気持ちを表す一文が入っていたからだ。 訴訟社会だからか、アメリカでは、 よほどのことがない限り、謝らない。 しかも全力でプレーして どうして謝る必要があるのだ。 最初の驚きは、時間がたつにつれて称賛に変わり 翌日の新聞には 彼の人間性をたたえる記事が並んだ。 松井選手のホームランに 思わず紙コップのビールを落とし、 タイムリーヒットに 近くの白人や黒人とハイタッチを繰りかえし、 あまり器用とは言えない懸命な守備に 手に汗にぎり、 チームメイトに信頼されている姿に、涙した。 一度だけ、夕食に 同席させてもらったことがあるが そこでも謙虚な態度は変わることはなかった。 どれもいい思い出だ。 キリがないのでそろそろ終わりにするが、 自分は異国の地での生活を楽しみながらも どこか不安で怖かったのだと思う。 多様な人種が暮らすニューヨークは 自由で活気にあふれ、殺気だっていた。 誰にも容赦しないこの街で 松井選手が活躍する姿を見て どれだけ勇気づけられたかわからない。 私にとって、ニューヨークでの生活は 松井選手の記憶と完全に重なりあっている。 マツイ! のホームランで勝利し、 フランク・シナトラの 「ニューヨーク、ニューヨーク」を 聴きながら、球場を後にした夜を ずっと忘れることないだろう。 そして今シーズン、 イチロー選手と黒田博樹投手が 敬意に満ちたスタジアムに 引き続き立つ。 物語は続いている。 (終わり) |
| 2013-02-15-FRI |
| きょうは、引退したゴジラと 特別なスタジアムをめぐるお話です。 |