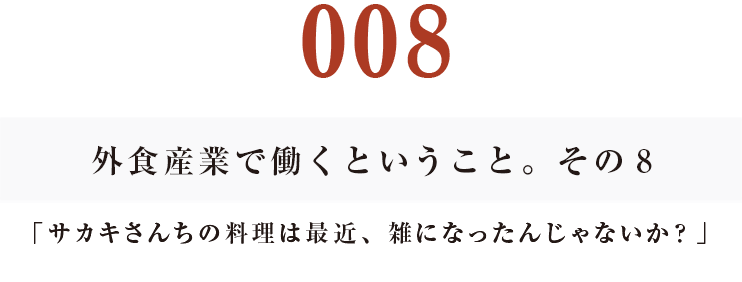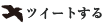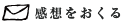焼き鳥を焼いてもおいしい。
刷毛で魚に塗ると照り焼きになり、
水で薄めただけで煮魚がおいしく炊ける。
それが鰻のタレ。
サカキ家が経営していた鰻屋の「普遍のタレ」は、
万能のタレでもあったワケです。
そしてその普遍にして万能のタレは
ものすごい匂いを発しながら仕上げるタレでもありました。
醤油を煮詰めて作ります。
悪臭というわけでなく、
おいしい匂いをギューッと凝縮させた匂いで、
ちょっと嗅ぐとお腹が鳴ります。
けれど何時間も嗅ぎ続けると、さすがに頭が痛くなる。
だからタレを作る作業場は
周りに民家がほとんどない畑のど真ん中にありました。
明り取りの天窓以外に窓のない倉庫のような建物で、
匂いが外に出ない代わりに中の温度はどんどん上がる。
夏なんか冷房をかけようが、
今のエアコンのように冷やす能力のないクーラーです。
生暖かい風がかき回され続ける中で、
汗だくになりタレを炊く。
作り終わって、それを瓶詰めするために粗熱をとる。
その間にお風呂に入って体をすっきりさせるのだけど、
よく洗ってもおかきのような
香ばしい焦げた醤油の匂いが体に染み付いている。
そうしてできたタレをお店に届ける前に
舐めて出来栄えを確かめる。
ほとんど同じように仕上がるタレではあるのだけれど、
人の手が加わる仕事です。
勘にたよる部分もある。
だから味の印象がたまに変わることがある。
今日のはほんのちょっとだけ塩を感じる‥‥、
あるいは甘い。
焦げた香りが少々華やか。
コクがちょっと浅いかしら‥‥、と、
そのときどきの味の印象を書いたラベルを
タレを収めた器に貼って店に配送します。
お店の厨房の調理人は、みんなまず、
タレを舐めてラベルに書かれたタレの個性を確かめる。
それから料理を作るのです。
料理を作るのは経験豊富な調理人でした。
だから鰻を焼く、その焼き方でタレの個性をうまくいかしていつも同じ蒲焼きに仕上げることができたのでした。

父はたくさんお店を作りたかった。
それもなるべくスピーディーに‥‥、
そうしないとモノマネ上手の人が
自分の店のようなお店を作って競争になってしまうからと、
お店を出すことをかなり急いだ。
タレを工場生産に変えた理由の一つは、
大量に出店する店に
大量のタレを供給しなくちゃいけないという理由。
もうひとつは、タレの品質を安定させれば
経験の浅い調理人にも、
決められた通りの味を再現するための
用意になるだろうと思ったから。
外食産業以前の飲食店は、
人が育ったらお店を増やす‥‥、というのが鉄則。
外食産業以降、
「人が育つスピードを超えた成長速度」
を実現する会社が続々あらわれて、
父はそういう会社に自分の会社をしたかった。
最初はうまくいきました。
経験の浅い人のみならず、経験のある調理人も
いつも安定したタレを使うと
安心して調理することができていい‥‥、
と生産性が上がったのです。
ところがそのうち、お客様からこう言われるようになった。
「サカキさんちの料理は最近、雑になったんじゃないか?」って。

まずくなったとは言われない。
おいしいんだけど、
盛り付けや焼き具合に
かつての繊細さがなくなったように感じる‥‥、と。
そのご意見はそのうちお店の雰囲気までに広がっていく。
ぼんやりした感じがする。
かつての元気がなくなった。
どこかよそよそしく感じるようになってしまった‥‥、
と、言われるようになったのです。
理由はにわかに判明せず、しばらく母がお店に入った。
厨房の中で調理人と一緒に働き、
そこではじめてわかった事実にびっくりします。
調理する人が味見をしない。
どうして? って聞いたら、
工場で作られたタレはいつも同じ状態。
だからいつも同じように調理できているはずだから、
味見をする必要がないと思って‥‥、と、
当たり前のように言うのだそうです。
「味見をしなくても確かに基準どおりに調理をすれば
同じ味になるのはわかるのよ。
けれど、味見をしないで作る料理に、
調理人って愛着を持てなくなるのネ。
だから盛り付けが雑になる。
雑な気持ちで調理された料理を運ぶ
サービススタッフにも、
雑な気持ちが伝わるのでしょうね‥‥、
たしかにサービスも雑に感じる。
しばらく働いていて、
ワタシのお店じゃなくなったみたいな感じがして
寂しかった。
誰にでも同じように作れる工夫。
それって、料理を作る人から
自分が作るものに対する愛着を
奪ってしまうことだったのかもしれないわねぇ‥‥」
と。
そういうコトがいろんなレストランで
当たり前のようにおこってしまう。
例えばイタリア料理のお店でのこんなコト。
来週お話いたしましょう。
2017-12-14-THU