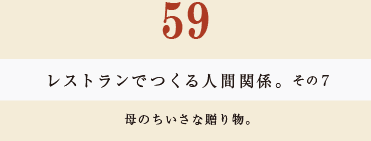身支度をしてホテルに向かう。
ボクは着替えてこざっぱり。
母は昨日のフラメンコダンサーみたいな格好のまま。
ホテルに入るや、かのコンシエルジュ氏と鉢合わせ。
ニッコリしながら、
「たのしい夜を過ごされたようにお見受けします‥‥」と。
彼が無理して予約をとってくれたレストランの
ステキだったコト。
お陰さまでニューヨークってこの街のコトが、
本当に好きになれたような気がして、
なにより息子の部屋に泊めてもらったんです。
朝、うれしくてサンドイッチをたくさん作って
残してしまって、だからよければ、
みなさんでお召し上がりくださいません? と。
恐縮です、とペーパーバッグを受け取る彼に、母は一言。
「でも、あのお店、私がコンシエルジュでも
日本人には絶対すすめぬお店ですわネ」
って、いたずらっぽく言ってペロッと舌を出す。
荷物をまとめに部屋に上がっていく母を見送りながら、
ボクは彼に「本当にありがとうございました」
と手を差し出した。
彼はその手をにぎって握手となって、そしていいます。
「またお目にかかれますよう‥‥」
さすがにここに住んでいると、
ホテルに泊まる機会はまずはないでしょうから‥‥、と、
ポツリと言ったボクの言葉に続いて彼は、こう言いました。
ホテルはお泊りになるお客様のためだけに
あるモノではないのです。
ホテルは街のすべての人のためにもあって、
だからこのロビー、このレストラン。
これらはすべて街の財産。
宝物。
ここでなくては叶わぬ夢や、
ここでなければ流れぬ時間を必要とする、
すべての方のためにあるのがホテルという場所。
そしてこの場所の使いこなし方を
誰よりも習熟しているのが、
私たち、コンシエルジュでございます。
ですから気軽に。
またお目にかかる日がまいりますよう、
たのしみにしてございます。
そう、彼はそう言い
ビジネスカードをボクにそっと手渡した。
生憎そのとき、ボクはまだ名刺のようなモノを
もっていなかった。
だから、申し訳ない、名刺がないので‥‥、
というボクに、彼はニッコリ。
その電話番号はワタクシへの専用ダイアル。
私が必ず受ける電話で、しかもあなたのアクセント‥‥、
スッカリ覚えてしまいましたゆえ、
名乗られずとも
お顔を思い浮かべることができましょう‥‥、と。
プロの言葉に、ボクは彼の名前の書かれたカードを
しっかと、手帳の中に挟んでおさめる。
そのビジネスカード。
驚くほどに見事な役目を果たすのですけど、
それはまだまだ先のコト。
次回からは、時計の針をちょっと戻してみましょうか。
ボクがキッチンの中で住んでるような、
へんてこりんなアパートに住む前のコト。
新人ニューヨーカーの戸惑い話をいたしましょう。
|