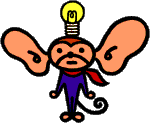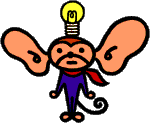|
#23 自分を信頼するための技術
「二一歳の学生です。初めて、コンビニ哲学を読みました。
言いたいことのすべてがわかったわけではないのですが、
今まで考えたこともなかった見方に触れることができて、
視野が広がったような気持ちに、なっているところです」
このようなメールをいただくと、とてもうれしくなります。
なぜかと言うと、このページで試してみたいことの一つが、
一般的な考えとしては、主流派になっているとは言えない、
「自分と折りあう技術」を紹介することだから、なのです。
現在、英雄と呼ばれる人の言葉は、多くが、
スポーツ選手や経営者の談話に代表されるものに見えます。
迷った人が手を伸ばす本や、つい見たくなるテレビ番組は、
「成功者による、将来の成功者のための、生き方指南」
のようなものが、ほとんどとさえ、言えるかもしれません。
仕事や家事や勉強に追われるように、毎日を懸命に過ごし、
「あっと言う間に、五年も十年も経ってしまったよなぁ」
と思ったことのある人なら、なおさら、そういう、手近な
「成功者の言葉」にしか、触れることができないでしょう。
忙しいので、多くの言葉の中から吟味する時間がないので。
しかし、成功者が成功し続ける最中には必ずあったはずの
丁寧に自分を見つめたり、自分自身と対話してゆく過程が、
特集のされ方や、インタビュアーや番組の意志によっては、
一言や二言のまとめとして、単純に、語られてしまいます。
あなたは、そういった類の特集に触れた後に、
「こうしたのだから成功できた。こうした方がいい」と、
ある方法が、まるでやらなければならない課題のように
語られて、そこに息苦しさを感じたことは、ありませんか?
そんなまとめが生まれる理由は、制作者自身が迷っていて、
手軽に自分を高める方法を求めているからとも思いますが、
同時に、不況の中、評価を受けなければ、不安になるから、
そういう特集の方が大勢に受けるため、でもあるでしょう。
しかし、
「読んでいる最中、絶えず自分が命令され続ける本」や、
「自分がやれることは書かれた命令に従うことしかないし、
内容を実行しないなら読む意味がなくなるような本」は、
却って、人を息苦しくさせてしまうときもあると思います。
最初の数か月だけは、その内容を覚えて実践したとしても、
いつか実践することをやめ、読んだことさえも忘れてゆく。
つまり、その内容は、自分の身体には、合わなかった……。
ある一つの命令に従うための言葉や、
自分を決まった鋳型にはめていくための言葉ではないもの。
それぞれのスポーツ選手や経営者の人生に詳しくなった後、
それを比較してしたり顔で品評することに飽きた人の言葉。
自分の、現在の立場や、今日やることについて、
自分自身とじっくり折りあうための言葉。
そういったものとしては、ほとんど、
「書画をたしなむ人の悟りを開いたような言葉」といった、
いくつかの限定された考えしか流通していないと思います。
感動的な身の上話は、世の中には溢れていますし、
スポーツ選手や経営者が、いかに自分を高めたかの過程も、
かなりいろいろな角度から、いろんな人が、語っています。
そういう言葉に刺激を受けて、自分も成功したという人も、
ある程度の数は、いるのでしょうが、
それぞれの行為に自分を同化してしまう以外の
言葉の受け取り方ができないままに、
「やっぱり、自分と天才とは、まったく違うだけだ」
と感じて迷っている人だって、多いと実感しているのです。
これは、「ほぼ日」に対して送ってくださる
大勢の人のメールを読んでいて、文体から感じたことです。
出世するためのノウハウとか、
世間の波をじょうずに渡るためのコツだとか、
自分の意見を、じょうずに相手に通す方法とか、
業績をあげるための、ちょっとした工夫だとか、
そういうものを身につけることも、もちろん、それぞれが
何かに勝つために、かなり必要なことなのかもしれません。
しかし、本人も気づかないままだけど、本当は、
そういう角度ではない好奇心を抱えた人が、沢山いる──。
「他人に評価されるように動きすぎるあまり、どこかで、
自分とつきあう方法や、自分を信頼するための行動が
ないがしろにされている」と感じたことのある人や、
「自分という度し難いものと向きあわないままでいることを
忘れようと、忙しさに身を預けている」人もいるはずで。
限りある自分の生活と、上手につきあう方法を探すことは、
難しいことではないのかもしれませんが、それにしたって、
世間で一般的に、いいとされている自分とのつきあい方は、
休暇にどれだけのお金をかけられるかという範囲を越えず、
「休暇がありさえすれば、自分自身と、
じょうずにつきあえるようになるという前提」が、
ほとんど、省みられないままだと、不思議に思いませんか?
周囲と和解するための方法論は、たくさんあるけれど、
自分自身と和解するための方法論は、あまり語られない。
理想の身体を保つ健康法は、ありふれていたとしても、
精神のゆとりにとっての健康法は、あまり、語られない。
たくさんの情報に触れるほど謙虚になるのはいいけれど、
たくさんの情報に命令されて、どんどん卑屈になることを、
さほどいいとは思えない人は、どう考えてゆけばいいのか?
そういう人にとってのヒントは、
哲学の分野じゃなくても、たくさんあるのだと思いますが、
哲学に見つけられることもあると、ぼくは、感じています。
とりわけ、ここで扱っているハイデガーのように、
「人は、限られた時間を生きる」という前提だけは崩さず、
切実に考えた人の言葉に、刺激があるのだと思っています。
だからこそ、気難しく見える多くの専門用語を抜かしても、
ハイデガーの言葉から自分なりに受け取ったものだけでも、
この場所で、伝えてみたいと思っていました。
彼は、主著の『存在と時間』で、
「いつか死んでゆく者としての人間」というものを、
まず、それぞれの人の前提として、大きく取りあげました。
他人に評価をされようと、そのうちに死ぬ存在なのですし、
自分の力で生まれたのでなく、他人に生かされたのだから、
自分を「投げこまれた贈りもの」のように受け取ってみる。
ある境遇に生まれることを自分の意志では選べないのだし、
自分の生がどう完成して、どのように死んでゆくかだって、
自分自身で知ったときには、もう、この世にはいなくなる。
そういう存在なのだとしたら、人は、いつでも、
「途中にいる存在」「生と死の間にいるかりそめの存在」
とも言えます。これが、ハイデガーの考える「人間」です。
「死を包みこむことで、生を愛する」という立場なんです。
「この世界が、死んでゆく者たちの住む家なのだとすると、
先に死んでゆく者を抱えつつ、自分も死んでゆくという
存在が、他人に対して言えるのは、いたわりの言葉です」
ハイデガーは、主著の中で、このようなことを述べました。
……そうすると、自分の経験や出身地を無視してるような、
他人からの見栄えがいいだけの鋳型に、自分を押しこんで、
安心しているというのは、他人とはうまくやれたとしても、
いつか必ずいなくなってしまう自分に対しては、
もしかしたら「優しくない態度」になるのかもしれません。
ハイデガーの書いた、『存在と時間』という本をめくると、
あちこちに、次のような意味あいの言葉が記されています。
「世間並みの一般性や、すでに調達されている世界に
埋没していることは、自分から逃げていることなのです」
既に世間で論じられ、解答のある問題を解くことと、
自分なりに、自分で望んだではいない境遇から出た問いに
自分の経験や考えのすべてを乗せて、立ちむかうこととは、
根本的に違うという話が、彼の哲学の大きなテーマでした。
だから、厳密ではないとも、後の人から批判されています。
しかし、人生論と哲学とがごっちゃになるような問いの方が
意味があるのだと、ハイデガーは自信を持って書くのです。
「この本では、『真実』についての問いを、
経験上の真実か、学問上の真実か、芸術上の真実か、
信仰上の真実か、ということにこだわらないでおきます。
普段から、厳密な定義もないままに、私たちが
『真実』と呼んでいるものにここでは注目したいのです。
一つの、特定の形態での『真実』を想像するというのは、
『一般者』という空虚なものを想定しすぎだと思います。
空虚なほど考えを限定し、高いところからものを見ると、
自分自身の根を、失ってしまうのではないでしょうか。
すべての現実的なものを無視して抽象的に考えることは、
おそらく、最もつまらない結果を生むのだと思います。
そういう『抵抗のない真空状態の考え』こそが、今まで、
世の中で哲学と呼ばれてきたものなのかもしれないけど、
『真実』という言葉が現に使われているものである以上、
実際に人々が、『だいたいは意味を掴んでいる』という
現実を無視するのは、始末に悪いのだと、私は考えます」
たとえば、ある本の前書きでも、ハイデガーはこのように、
現実と哲学とを、いったんごちゃごちゃにしたところから
言葉をつなぎ、自分が感動した言葉を引用するところから、
考えを、進めてゆこうとしたりします。
ハイデガーが書いた膨大な量の哲学書の
ほとんどを読んだ後になると、彼が、どのような方向で、
どのような境遇で考えているかだけは、明確にわかります。
彼が、何を「自分の根」だと感じたかも、伝わってきます。
他人が論じた内容や、他人から借りた議論を続ける限りは、
その人本人の肚の底から出た言葉は、見つけられないけど、
ハイデガーの場合は、おそらく、頑固で怒りっぽいだとか、
本を読んでいると、そんなことまで、伝わってきてしまう。
彼が、先人の言葉をもとにして
ツギハギだらけの状態であっても真剣に考えたことを、
彼なりの境遇で、感情と共に、ぶつけてくれたからこそ、
そのツギハギは、未完成なまま、生き生きと読めるのです。
彼の書いた哲学書自体にも、客観性はあまりないからこそ、
「自分の経験から出発して考えをふくらませるヒント」や、
「客観的に何かを言ったつもりでも、自分自身の考えが
一つも出ていないことから抜け出す方法」を求める人の、
足がかりになるのではないかと、ぼくは思っているのです。
自分が、
「死ぬまでの短い間を生きる途上にいる存在」
であるという事実を受け入れて、世界の中に、あらかじめ、
自分の知らないまま、贈りもののように与えられた居場所。
それをねぎらうようにして、ものを考えはじめてゆく……。
同じ問いに迷っている限りは、
その問いはまだ自分にとって切実なのだと考えて、
その問いに留まり続け、更に何度も考えなおしてゆく……。
この辺が、ぼくとしては、ハイデガーの「考える癖」だと
感じていますが、そのあたりは、別の機会に紹介しますね。
あなたは、今回の話に触れて、どんなことを思いましたか?
あなたは、自分自身の経験したことを、誇りに思えますか?
最後に、参考までに、
最高に効率のいい生活だけをしているわけではない中で、
抵抗があるからこそ、考えたことについて、職人の方から、
ぼくがかつて直にうかがった談話を紹介したいと思います。
「実際に、アメリカで生活しながらだと、
どう生活拠点を置くとか、
子どもをどう学校に行かせてとか、
短期の出張とは、話が、ぜんぜん変わってきます。
アメリカを見る気がしますよ。
アメリカの中に入っていくわけだから。
もちろん、中に入ったら、国民性の違いで、
どれだけアタマに来ることがあるか……。
でもそれは、アタマに来てもしょうがないことで。
われわれ、アメリカでは外人なんだから、
向こうに入っていかないといけない。
悔しい思い? 当たり前よ、カルチャーが違うんだもん。
でも、違う、違うって言ってはおれないから、
中に入っていく……それは、ハンパなことではないです。
だから、その経験は、
自分の中では、めちゃくちゃものを言っていると思う。
家の中での役割だってあるし、
『子どもがいなければ』とは、正直、何度も思ったよ。
子どもさえいなければ、どこだって暮らせるけど、
子どもがいると、海外ならなおさら、
学校の設備が整ったエリアに行かなければならない。
そしたら当然、何のためにアメリカに渡ったんだろう、
というような現実も、人づきあいのわずらわしさから、
もう、何もかも、抱えこまなきゃいけないわけです。
でも、抱えこまない自分がいたら、たぶん
ぼくの人生は、絶対後悔するものになったと思います。
わずらわしさも、ときにはPTAさえも抱えこんで、
家庭で、父親を張らなきゃいけないことも抱えこむ。
これは、あとでモノを言ってくるんですよね。
わかります?
『子どもいなかったらどれだけラクか』
と思った時期もあるし、やっぱりその後で、
『抱えこまなきゃいけなかったっていうことは、
どれだけまた、よかったことなんだろう』
って、思いなおしたりも、するんです。
そういうことも経て、自信が生まれてくると思います。
朝に子どもを学校に送る時間が、とてもいいんですよ。
子どもたちを、ガーッてクルマで送ってるとき、
「あ、絶対、今のオレのほうが勝ってる。
学校に子ども送ってるオレのほうが、
前のオレよりも、絶対にかっこいい」
と思うことがあるから。
本当は、どこかいい会社に抱えてもらって、
高給をもらって、作品だけ作っていたら、
それはもう、どんなにラクかと思ったこともあるけど、
そしたら、あるとき、ハッキリ言われたことがあるよ。
『それをしたらしたで、あなたは絶対ムリだから』
きっと、そうですよね。自分でもそう思う」
これまであなたが邪魔だと感じてきたことに、自分なりの
出発点があるかもしれない、と思ってふりかえってみると、
あなたのこれまでの境遇や経験の数々は、どう見えますか?
次回に、続きます。
あなたが、読んだ後に感じたことや考えたことなどを、
メールで送ってくださると、とてもうれしく思います。
postman@1101.com
件名を「コンビニ哲学」として、送ってくださいませ。
木村俊介
|