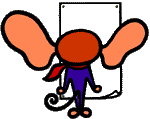|
134枚目:「カラフルの花」
春の新作を食べてますか?
新製品のうんちを出してますか?
新製品のカロリーで歩きまわってますか?
でもそれはそもそもの目的ではなくって
新しい何かを手に入れるドキドキが欲しかっただけだから
新製品の新製品の新製品の…
いまは何にむかって歩いているのですか?
はじめからドキドキが商品として売っていたら
それもフィリピンバナナみたいに安く叩き売っていたら
そんな世界で、仕事に打ち込んだり、恋人のことを想ったり、
本を読んだり、映画をみたり、絵を描いたり、
かっこいい服を買ったり、部屋をかたづけたり、
そういう類の面倒なことは一切がっさい
もうどうにもこうにもやる気がおきないと思うのですけど
どうですか?
遠い未来かも知れないし、それほど遠くないことかもしれません。
人口が多くなりすぎて全員が活動できなくなった頃かもしれないし
価値観が崩壊して刹那主義に傾倒した世界かもしれません。
ともかく
脳内物質を自由にコントロールする安全な錠剤のようなもの。
いつかの未来にそれが開発されました。
自分の能力ぎりぎりの仕事を達成したあとのまんぞく。
誰も考えつかないことを思いついた時のうれしさ。
恋人がやってくるのを待っているせつなさ。
おいしいものを食べて全身にひろがるしあわせ。
マラソンをして走り終わったあとのけだるさ。
そんなあらゆる感覚と感情が色とりどりの錠剤をひとつ飲むだけで
体一杯ひろがるようになりました。
自動化された工場が半永久的に錠剤を排出して
自動化された生命維持装置が人類の数を保って
自動化された防御システムが都市が緑に覆われるのを防ぐ。
そんな銀色の超巨大都市が建造されて
夢見がちな楽園は何百年もそのまま密林の中にたたずんでいました。
都市の建設から数世代後。
もはやその頃には錠剤の呼び起こす感情が
そもそもなんと呼ばれていたのか。
恋や労働や芸術や奉仕やそういう…
行為というものの概念自体が既に失われていました。
そこは保証された結果だけがプロダクトとして生産され続ける世界です。
でも。寓話的で作為的な物語の語り手である私は
この銀色の超巨大都市に天変地異をひきおこします。
ある晩、防御シールドの間隙をぬって
銀色の都市にねずみが1匹迷い込み
コンピューターの配線か何かを囓りました。
がりがりがり…。
ちゅんちゅんちゅん。
次の日の朝、システムの停止した銀色の都市で
夢から目覚めた人間達は途方にくれました。
なんだか人間達はお腹がすき、さむく、心細く思いました。
もちろんそんな言葉は彼らにはなかったので
いうならば「緑色の薬と黄色の薬と赤色の薬が足りなかった。」です。
都市のコントロールパネルのランプは全てまっ赤になって
異常事態を宣言していました。
いくばくかの残された薬をめぐって殺しあいがおきました。
自分で自分をおしまいにする人間もいました。
仕方なく銀色の都市を出ていった人間もいました。
都市の外、広がる密林の中には
小さな果物がいくつか実っていました。
ある背の高い男はそれをみつけるともいで囓りました。
甘く、香気が口中にひろがりました。
それは緑色の薬と似た感じでした。
男はたくさん実を持ち帰って
都市の人間にわけてやりました。
こんどは青色の薬と似た感じでした。
木の実に届かない背の低い男は悩んで…
疲れた男の前で踊ったり、変な顔をして楽しませては
そのわけまえにあずかることにしました。
それも青色の薬と似た感じがしました。
踊りをみていた女がひとり
赤色の薬と同じ気分を味わっていました。
その女の横顔をみていた男も
また赤色の薬によく似た感じだったりするのでした。
人間達は錠剤がなくても
同じ効果を生み出す方法が
自分たちに備わっていることに気がつきました。
そして物語はここでおわります。
いつかまた世界は灰色にくすんで物語は最初にもどります。
これは寿命のぶんだけネバーエンディングな物語です。
Shylphchov Musaborizky III
Mail shasho-san@hinden5.com
HomePage http://www.hinden5.com
|