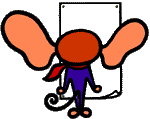63枚目: 「ともだちのはなし」 Ver2.00
I .
今日は僕の友達の話をしようと思う。
といっても転校してからというもの
クラブも課外活動もしていないので、
僕に友達は二人しかいない。
そして困った事に、その二人とも電話を持っていないのだ。
だから僕は、一千万人の住む町に住んでいながら、
いつも均質で同じ声の時報のお姉さんぐらいしか
電話を掛ける相手がいない。
その日は四月の終わり、緑の日の前日だった。
朝から小雨続きで湿度は高く。黄色い傘を差して、
薄手のセーターを来て歩いていると、いったい
暑いんだか寒いんだか自分でも分からない天気だった。
教習所から帰って八時頃。
部屋に転がって、借りてきたスノーマンを
アンテナの繋がっていない小さなテレビデオで見ていた。
借りてくるのはこれで八回目位だから、
テープを買った方が安いとも思う。
「八十日間世界一周」や「天空の城ラピュタ」と同じ様に、
年に何回か僕は発作的にこれが見たくなって
借りてきてしまうのだ。
とりわけスノーマンは映像も音楽も大好きな一作だ。
取り合えず、そうして雪だるまの溶けそうな
四月の二十八日。僕はスノーマンを見ていた。
そして唐突に。
(もちろん電話はいつも唐突に鳴るものだけれど。)
特別の唐突さ加減で、電話が鳴った時は驚いた。
電話はどこにおいてあっただろうか
回線を引くとお金が掛かるので、
僕はDDIのポケット電話を使っている。
PHSはとても小さい上に、滅多に使わないので、
電子音を頼りにそれを見付けるまで、
コールはたっぷり十回を数えていた。
『ピー、ガチャン』
通話ボタンを押すと聞こえた、コインの落ちる音。
公衆電話からだ。
「もしもし?」
「ススムか。今、鮭の野郎と用賀駅にいるんだけど、
お前も来ないか?」
「C7、僕の電話番号知ってたっけ?」
「そりゃ、前にお前が自分で話してたじゃないか。
オムオム白い恋人…なんて、北海道土産みたいな
語呂合わせまで丁寧に説明してさ。」
…C7は乱暴な癖に細かい事を良く覚えている。
雨の降っている中、部屋で一人ビデオを見て、
暖かい紅茶でも入れようかという矢先だ。
少し…いや大分、これから出かけるのは面倒だった。
画面の中では男の子が雪だるま作りを一時中断して、
母親に呼ばれて暖かそうな紅茶を飲んでいる。
一面の雪野原を窓の外に見ながら飲む
暖かい紅茶は、とても美味しそうだ。
けれど、出てこないかと言われたら、
出ていかなければならない気もするし…
二人が揃っているのならなおさら、
だって彼らは大事な友達だ。
まだ全然乾いていない黄色い傘を再び開くと、
僕は用賀駅に向かった。
小雨は風に流され横から降ってくるので
靴やチノパンが濡れて足元が冷たくなる。
湿度と、もうじき来る初夏を思わせる大気が、
既に日は落ちたというのに不快指数を
かなりの高レベルに保っていた。
僕は、鮭とC7に会った日の事を思い出しながら
駅へ向かって歩き続けた。
II .
学校というのは実に狭い世界で、
普通に過ごしていては、
なかなか鮭やC7に出会う事は無い。
僕が初めて鮭に出会ったのは渋谷のタワーレコードで、
それは全くの偶然だった。
五階の売場でPONTA・BOXの限定盤を
クルクル回して眺めている鮭を見た時、
僕は非常に興味を持ったのだけれど、
幾ら相手が"鮭"とはいっても、
いきなり話しかけるのには気後れがして、
僕はそのまま店を出てしまった。
そして。次に鮭に合ったのは、
用賀駅ビル内のツタヤでの事だった。
ロリンズのCDを持って、「バボッ、バボッ、バボッ」と
テナーサックスの真似をしていた鮭に、
僕は偶然や確率を超えたものを感じて
思い切って話し掛けた。
二人とも夕飯を食べていなかったので、
二軒隣のファースト・キッチンで一緒に夕飯を食べた。
隣に京樽もあったのだけれど
心なし鮭の顔に翳りが見えた気がして、
僕は何も気付かないふりをしてファースト・キッチンを選んだ。
「ぼ、ぼくは鳥肉の味なんてわからないんだな。」
鮭はそんな事を言いながら、タンドリーチキンを食べた。
タンドーリにしては癖が無さすぎる気もするが、
これはこれで結構旨い。
鮭は"鮭"なので、お金が無いらしく、
僕は鮭の分も支払ってやった。
C7。本当はラックスマンコントロールアンプC7
なのだけれど略してC7と呼んでいる。
彼は結構作りからして乱暴な奴で、
気がついたらオンキョーのA-1Ever2の代わりに
電源コードを奪って居座っていた気がする。
彼に会ったのは秋葉原のジャンク屋。
AKI80なんていう絶滅寸前の
8bitマイコンの山の隣に積まれて、
やる気なさそうに煙草を吸っていた。
僕のたった一人の友達が"鮭"だと聞いた彼は、
「俺も友達になってやるよ。」と言ってきた。
きっと彼も友達が居なかったのだと思う。
だって三人は全然違うのに、
それからというもの結構気があったのだから。
今度は三人で渋谷のメラでカレーを食べていた時の話だ。
「痛ッ」と鮭が口をしかめた。
口の中に傷が沢山あるらしく理由を質すと
最初は照れていた彼だったけど、
終いには長々と魚類特有の瞳を輝かせ打ち明けてくれた。
鮭の悩みと傷の理由を要約するとこうだ。
鮭は恋をしていた。
そして鮭が好きになった相手は"鮭"では無く、
ルアーなのだそうだ。
山水の青いルアー。
鮭の奴はその青い羽毛の美しさを、
本当に幸せそうに、そして長々と、
僕とC7に語った。
しかし鮭にとって"鮭"では無く、
ルアーに恋をするのは道ならぬ恋であるし、
「仲間の"鮭"にしてみても、ぼくは異端なんだな。」と
やや古風な言い回しで、鮭は悩みを話し続けた。
ついあの青い羽毛を飲み込んでしまいたくて、
鮭は銀色の鉤針にもめげずに何度もそれを飲み込み、
そして人に釣り上げられては、死にそうな目に遭ったという。
「もう、こんなのやだよぅ。」
鮭は涙目になっていた。
その次に三人で待ち合わせをした時。
僕は上州屋に寄って山水のルアーを買って行った。
sansuiのマークの入った青いルアーは
千円もしない買い物だった。
C7の提案で、待ち合わせはソニープラザの中で、
そんな所で上州屋の袋を提げているのは僕だけだった。
酒で、銀白色の腹を紅潮させた鮭。
僕の差し出したルアーを前に、
妙に態度が演技掛かって大袈裟になっていた。
C7はにやにやと、そんな照れた
鮭の様子を肴に楽しそうに飲んでいる。
「いいよ、悪いし。ぼ、ぼくは。」と
鮭はC7の手前、ルアーを拒絶していたけれど。
後で、「やっぱ、ほしいんだな。」と
二人きりになった時に言ってきた。
僕はそんな鮭を素直で可愛いと思う。
III .
用賀駅の即席ギリシアコロシアムの様な、
半円状の階段を降りるまで、
僕は黄色い傘の下でそんな二人の事を思い出していた。
でも、今日は突然どうしたんだろう。
鮭が川に帰るにはまだ早いし、
C7はしばらく仕事で忙しくて会えない筈だ。
…そして、雨に滑らないよう
慎重に階段を降りていて、気が付いた。(!)
今日は僕の誕生日だ。
つい自分でも忘れていたけれど、
その事で二人は集まったり、
十円玉を探して拾っては
慣れない電話を掛けたりしてくれたに違いなかった。
DPE店の角を曲がって、
二人を驚かす登場の仕方を考えながら、
僕はちょっとばかり嬉しくなっていた。
illust:Kohji-3200

shylph@ma4.justnet.ne.jp
シル