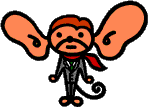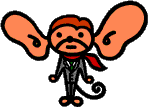| 田坂 |
過去は、ちょっと調査をやると
500万とか1000万とか簡単にもらえていて、
シンクタンクは楽な商売だったんですけど、
そういうのが、だんだん通じなくなってきた。
そうなるべきだと私は思っているんです。
3万人調査したら、という
科学的なものではなくて、
「先週原宿を歩いていたら、こう思った。
やっぱり時代はこれですな!」
それで通用するようにならないといけない。
・・・けっこう野蛮な発言ですけども。 |
| 糸井 |
そのやりかたでは、
自分の感覚がが死んだときには、
共倒れになりますよね。
「俺の薦めたものがよくなくなるのでは?」
と、ある年数が経つと、
そういう危険性を怖れはじめますよね。
でも、死んでいない人が、たまにいる。
最近では、邱永漢さんがそうです。
全然死んでいない。あきれますよね。
シンクタンク的なものの見方より、
あの人の言うことのほうが、当たっています。 |
| 田坂 |
「予測」って一体何なのかという議論がありますが、
つまり、ある人の言う通りになったときに、
その人が予測をしたのか、
その人の言霊が世界を別の方向に持っていったか、
わからないところがある。 |
| 糸井 |
邱さんなら、もうひとつメタなレベルなんです。
科学技術が進歩するから、
これからどういう発明や発見が生まれて、
どのような事業が起きるのかということを、
技術のひとに会ってきかなければ、
と邱さんが思ったのが、昭和36年なんですよ。
・・・この、レンジの長さ!
株屋さんは、商売になりはじめてからですが、
生む場所をコントロールしている人に
まず会おうとする。かっこいいでしょ?
他にも、梅棹忠夫さんは『情報の文明学』で
今ある状態を全部書いているんですよ。
びっくりしちゃって。
土下座したくなりましたよね。
動きが出てから秀才が集まるんですが、
天才はそれを遠巻きにして、
「それじゃない」といっているだけ。
田坂さんはそこに行きたいと、今、思っている。
ぼくのことで言うと、
今から天才になるのは無理だけども、
竹林の七賢人のようなひとのケーススタディーを、
尊敬を交えて研究することは、してみたいなあ。 |
| 田坂 |
私、経営学の本を読まないんです。
どうしてかと言うと、
経営学者の論じていることは、
全部「後追い解釈」だから。
過去をふりかえって、
あれはこうなったからこうだ、
と分析して物語にしてすっきりしているけど、
未来に適用できるかというと、ほとんどだめで。
だから、ちょっと失礼な言い方になりますが、
おんなじ分野の二流の人の話をきくよりは、
別の分野の一流の人の話をきいたほうが、
絶対に参考になるんですよ。
世界のものの理(ことわり)というのは、
分野を問わずおんなじだと思うからです。
プロの一流という世界があるならば、
分野を問わず、ものの理(ことわり)の世界まで
行っちゃったひとなんですよ。
物の理(ことわり)なら物理だし、
心の理(ことわり)なら心理でしょう?
人の心の理(ことわり)がわかれば、
ビジネスもほとんどわかるんです。
緻密な言葉でしゃべらなくても、
「何となく時代はこっちに」
「きっと次は、ああなるよ」
それは難しい方程式の話ではなくて、
水が必ず低いほうに流れていくような、
ある理(ことわり)があるんですよね。 |
| 糸井 |
そういう天才たちって
「だって、もう、そうなってるじゃない?」
と言っているんです。
ぼくなんかにも、天才瞬間があるんですよね。
ぼくは基本的に凡才なんだけど、
天才の瞬間があって、そのときには、
「もうとっくにこうなってるじゃない?」って。
でも、早すぎて、人から見ると、
まだほんとにそうなっているとは、
なかなか思えないんですよね。
売れるに決まっているタレントは
ずいぶんいるのに、
プレゼンテーションをすると、落ちるんです。
最初の頃の木村拓哉くんも、
調査に出ていない新人だったから、そうなって。
「前に糸井ちゃんの言ってたの、使えない?」
と言われても、「2年遅いよ!」みたいな。
みんながワーキャー言ったときにはじめて、
「お金はいくらでも出すから、
あいつを使わせてくれない?」
と言われても、遅いんですよね。
理(ことわり)のわかっている人というのは、
たぶん「もうそうなっちゃってる」人だと思う。
邱さんが証券会社の株を買いなさい、と言う。
株を扱う人が多くなるから、総取引額が多くなる。
株は手数料で成り立っているから、
証券会社は儲かる。
前のバブルのときのイメージが悪すぎるから、
そこのところで株価が安くなっている。
そうしたら、そこの高騰する幅が一番大きい、
こういう説明には、誰も反論できないですよね。
誰も言わなかったんです。
邱さんが言ったから、ではなくて、
理屈があっていたからだと思います。
こういうことが、
きっといろいろなところであるんだと思う。 |
| 田坂 |
普通の人に見えないものが見えるというのは、
言葉にしてしまうとそういうことでしょうね。
なぜ見えるのかは、
それだけでも大議論があるくらいにおもしろい。
もののよく見える人は、おそらく、
タウンウオッチングをよくやるひとなんでしょう。
テレビで言うと、ザッピングをするひと。
情報みたいなものが、自分の体をろ過すると、
自然に何か残っている、みたいなね。 |
| 糸井 |
本の早読みとか、買うだけでいいんだ、
という理屈もそうですけど、並列処理なんです。
別のことを考えているというのが、
一番重要だと思うんですね。
つまり、ぼくの天才瞬間は、
違うことをしているときなんです。
一番いいのはパチンコ屋。
うんこしているときとか、お風呂、運転。
本来やっているはずのことが退屈しているときに、
どうしても呼びこまなければいけない考えが、
降りてくるわけですよ。
例えば、うちのスタッフのひとりに、
本を読むのがものすごく速い奴がいるんです。
たぶん、読んでいないんだよ。
つまり、筆者のロジックを、
筆者の出す順番では追っかけない。
追っかけた瞬間に、並列処理ができなくなるから。
並列処理をやらないから、
みんなが秀才になっていって、
一冊ずつ本を読むことが本当に疲れるし、
街を歩いていても
「ビジネスのネタを探そう」となると
その目しかないから、何も見えなくて、
今、自分の横を通りがかったすごいものに
目が行かなくなる。
「きょろきょろしている子供になれ」
ということだと思うんですよ。
社会人になると、それができないので、
だめなんでしょうね。 |
| 田坂 |
すごいアイデアが出てくるときって、
大体おんなじパターンで。
前日とか前々日ぐらいに、
すさまじいくらいにある問題意識で考え抜いて、
でも答えが出なくて
「よくわからないな、疲れた」と一度忘れる。
でも潜在意識には、しっかり入っていて、
別なことを考えているときに、ふっと思いつく。
アイデアが出るときは、ほとんどそうです。
そうすると、敢えて意図的に
議論をしていても答えが出ないだろうな、
と思っていて、
テーマが心にしみわたったというあたりで
「もういいや、疲れたから寝よう」
「ラーメン食いに行こう」
とやって、あとは潜在意識の世界に任せる。
そうやって、潜在意識の
マネジメントをするときがありますね。 |
| 糸井 |
ああ、やっぱりそれは意識的に
いろいろなひとがそうやっているんですか。 |
| 田坂 |
そう思います。
司会の役をするときに、
「これだけばらばらなことを言われると、
どうやってまとめよう?」
という瞬間があるんです。
はじめはどうしようと思っていたけど、最近は、
「あ、この先生がしゃべり終わったころに思いつく」
と感じるのです。
すると、しゃべり終わる3秒前ぐらいになると、
必ずキーワードが3つぐらい浮かぶんですよ。
そのとき「ああ、この言葉でまとめちゃおう」、
みたいな。
そういうの、ありますよね? |
| 糸井 |
あります。司会という役で
リーダーシップを取っているときには、
「ここで俺が戦わないと、
この戦いが『ないこと』になっちゃう」
という切羽詰った緊張感、
エマージェンシーコールみたいなものが
発言を生み出すものなんじゃないかと思います。
そこがおもしろいんですね。
(つづく) |