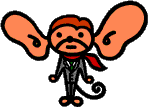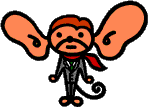| 田坂 |
特定の商品を、どうやればたくさん
買わせられるかというマーケティングは、
実はWindowsでもう大体尽きたと思うんですよ。
徹底的に買わせたという意味では、
Windowsは歴史に残るくらいです。
その対抗勢力として出てきたのが、Linux。
あれは、つくる側と使う側が、
全然分離していないんですよ。 |
| 糸井 |
まったくそうですね。 |
| 田坂 |
Linuxを見ていると、
従来のような、デファクトにして、
買わざるを得ない状況をつくりあげて
世界中に買わせてしまうというパラダイムが、
終わりつつある。
作る側と使う側が一体になって、
そこにものが生まれている。
複雑系の科学でよく使われる
「創発」という言葉は
「emergence」という英語の訳ですけど、
秩序や構造をおのずからつくるという、
自己組織化のことなんですよ。
実はマーケットにおいても、これから生じるのは
極めて創発的で戦略的な出来事で、
誰も設計もしていなければ、
たくらんでもいないし、
シナリオを書いているわけでもないけど、
あれよあれよという間に物語ができていたり、
何かがやってくるんですよ。
それに対して、こちらとしては、
手をこまねいて待っているだけではなくて、
非常に深いレベルで
創発を促すやりかたがあるんですよ。
細かく操作しようとするのではなくて、
場をとことん活性化していくというか、
何が出てくるかわからないけど
とりあえず言霊を投げこんでみるとか。
そういう「創発戦略」が、これからの
企業戦略のパラダイムになると思います。 |
| 糸井 |
インディアンを思い出すんですよ。
狩れる動物はたくさんあっても、
どれだけ食えるかということで追う。
たくさんは殺さない。
Linuxでビジネスをやるとしても、
第2のマイクロソフトはつくれないです。
つまり、中規模の利益を当てにすることですね。
Linuxという川に船を浮かべるという
イメージですよね。船一艘ですから
乗る人間の数もたかが知れているし、
みんなが使ったところで、利益も膨大ではない。
この「ノーリスク・ミディアムリターン」が、
うちのキャッチフレーズなんですけど。 |
| 田坂 |
なるほど、それはいいですね。 |
| 糸井 |
ローリターンだと、食っていけないですから。
それに、情熱のすべてをかけるくらいの
やる気はあるわけです。
その仕事を維持するための精神的なコストを
すごくかけているので、ローリターンでは困る。
でも、もしハイリターンを狙ったときには、
絶対に枯葉のように死んでいきますね。
だから、ミディアムリターンでどう辞めるか。
もしその仕事がここまでだと思ったら
誰かがあとを継いで、つまり社長が変わる。
ほかのかたちでは商品になるだとか、
ソフトはつもそういう育ち方をしていますよね?
そういうミドルリターンの方法を
どっかで見たなあというのは、インディアン。 |
| 田坂 |
なるほど。インディアンという、
再び注目されている世界観のあたりを
引用されるのが、さすがだなと思います。
それと関連しておもしろいと思うのは、
Linuxの成功の要因のひとつが、
リーナス・トーバルズの
人柄の良さだということです。 |
| 糸井 |
あっ、わかる。 |
| 田坂 |
あの人はすごく無欲で、
「使い勝手のいいソフトならいいんだ。
みんなに喜んでもらえばそれでいい」。
という発想です。
主張するのは、ソースコードの最後に、
「私もここを改良した」と掲載するくらい。
その程度のエゴとも言えない
誇りのようなものでやっているだけで。
時代の人になってからも全然おごらず、
「いや、自分はそんなつもりはなかった」。
と爽やかにいう。
これからは、ビル・ゲイツ的な
メンタリティよりも、ああいう人柄じゃないかと。
資本主義が徹底的な合理化と効率化を
進めたけど、そのかわりに、
非人間性みたいなところに向かっていった。
だから今、人間性に戻ってきているんですよ。 |
| 糸井 |
自分の動機を失って商売をするんじゃなくて、
お客さんが買う買わないを考えないで、
つくりたい、欲しい、つくりたい、欲しい、
いいものができなかったら出さないでいれば、
ミディアムリターンであればできるよ、
という発想で、今うちはやっているんです。
でも、スタッフの人数から言うと
実は一杯一杯に近くて、
小さなクレームまで含めて
全部には対応できなくなるんですよね。 |
| 田坂 |
そうでしょうね。 |
| 糸井 |
重大なミスをしたときの、
読者からのメールは、痛いですよ。
だから、日曜日でも
ぼくは丁寧に返信メールを書きます。
欠損品が出るとか
ちゃんとした対応ができないとかいうのは
ある確率で、必ず事故としておこりますよね。
その事故をきれいにフォローするには、
まだ、うちの組織は弱すぎるので、
へとへとになってカバーするしかないんです。
野球の選手が1軍で練習しているときに、
海のほうまで飛んでいってしまった球を
取りに行くひとがいるのですが、
球団代表とかが、それなんです。
選手の拾いきれない球を、球団代表が拾う。
ジャイアンツの練習を見に行っていて、
あれは美しいと思いました。
人柄がいいんですよ。
「いやあ、いいなあ」って言ったら、
「だって、ぼくはこういうことしかできないから」
明るく拾ってるんですよ。
日曜日にぼくがメールを出すのは、
きっと、そういうことなんですよね。
空いているやつが、
一番つまらない仕事をするというか。
でも、それが実は一番大事、みたいな。
これは今までの組織体系では、考えられない。
うちはEコマースの代表例としては出ないで、
「イトイのところは、ちょっと別扱いだ」
みたいになっているけど、この延長線上に、
明るい場所があるなという気はしているんです。 |
| 田坂 |
クレームについては、
ほんとにその場にいると大変だと思うんですけど、
少しマクロに見ると、
コマースとコミュニティーが、
もう、融合して来ているんですね。
ですから、ものが売られてゆく場面というよりも、
買い手という名の人と、売り手という名の人が
みんなでわーわー言いながら、
クレームをつけてみたり、
ごめんなさいとあやまったりしながらも、
人間同士のコミュニケーションをやっている。
今までは、機械的に、
ただ流通が整備されていて、
品物にクレームを出しても
「まもなく慎重に対処いたしますので」
と戻って来るような習慣が、
ずっとあったと思います。
それが今、コマースとコミュニティが、
もう融合してきていて、不可分でしょうね。
ものを買いたいからある場なのか、
コミュニケーションをしたいからある場なのか、
もうわからなくなりますよね。
そういうすごいおもしろい時代になっていて、
そこはむしろ堂々と、前にやっていたことを
やめてしまっていいと思うんですよ。
前のパラダイムでは、売り買いの場と
コミュニケーションの場を分けたけれど、
昔に「市場」(いちば)と呼ばれていたころには、
実は売り買いとコミュニケーションが一緒だった。
今だって、魚屋に行くと、
「奥さん今日きれいだね。安いよサワラ。
こうやって食うとうまいんだよ」
なんて、コミュニケーションをしながら
ものが売れてゆくでしょう?
いったん分離して、また戻ってきた。
インターネットって、
そうやって螺旋的に発展しているので、
おもしろいことが起きていますよね。
昔の市場は100人だけだったけど、
今はもっと多い。 |
| 糸井 |
遠さや距離も、気にならなくなりましたよね。
これまでは体温が届かない距離はだめでしたけど、
今、体温って、電波に乗って走るんじゃないか。 |
| 田坂 |
そのとおり、それ、大賛成です。
(つづく) |