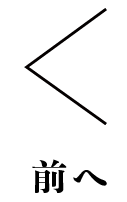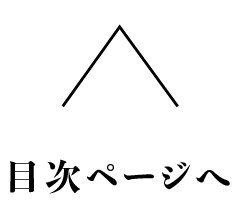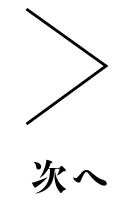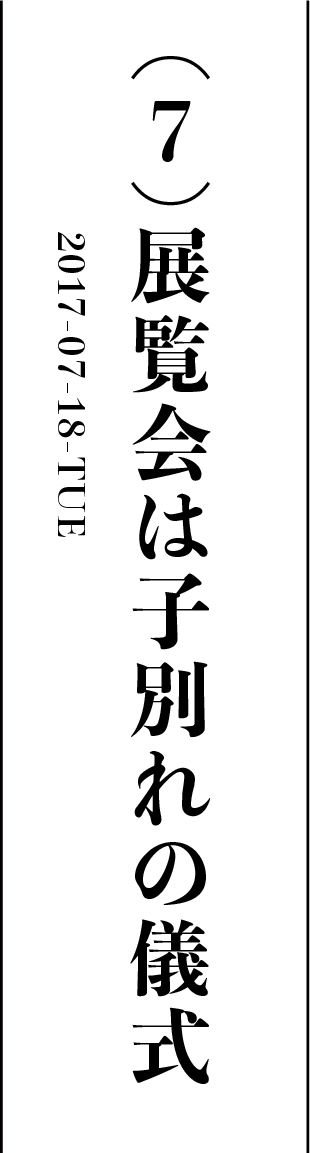
- 糸井
- 石川さんの展覧会のポスター、
これは何が書かれているのでしょうか。
- 石川
- 『歎異抄全文』です。

- 糸井
- へえー! こんな書体もあるんですね。
- 石川
- これは29年前、バブルの頃ですかね。
- 糸井
- 読もうとしたら、
読める文字があるんですか。
- 石川
- 「弥陀の誓願不思議に助けられまいらせて‥‥」、
現物はね、もっと大きくて、
ちょっとすごいですよ。
- 糸井
- もちろん、今回の展覧会には出ますよね。
- 石川
- もちろん、出ます。
- 糸井
- これは、筆で書かれているんですか。
縦線も、横線も。
- 石川
- 普通の筆です。
筆は何にでもなるんですよ。
- 糸井
- この、まっすぐな線は、
意識なさってるんですか。
- 石川
- もちろん。垂直芸術ですから。
- 糸井
- いやあ。ものすごい、まっすぐ(笑)。
これはでも、速度が追えそうにないのですが。

- 石川
- いや、ずっとなぞって書いてみられると
わかるはずですよ。
そんなに速くは書けません。
すーっと書いたら、揺れますから。
- 糸井
- なるほど。
- 石川
- 筆先で刺していくように書くんです。
- 糸井
- 刺繍みたいに。
- 石川
- そうそう、そうそう。
- 糸井
- この上に書いている「書だ」という文字は、
速度感を感じやすいですよね。
そのまま見ても、「おおっ!」となる。

- 石川
- そうですか。
- 糸井
- ぼくが興味を持っているのは、
石川さんが書かれている中で、
反故にする、捨てられていく書っていうのは、
何があるんでしょう、ということです。
たぶん、反故もたくさん作ってるわけですよね。
- 石川
- 反故になるっていうものは、
筆を下ろしたときの、
「さわり」が予想したものと
違っている場合ですね。
その「さわり」で、
だいたい第一画がどのように
仕上がるかがわかるんですけどね。
- 糸井
- あ、そうですか。
第一画で、もうわかる。
- 石川
- 最初の文字の第一画の具合ですね。
それでもう、失敗だっていうのはわかります。
最初の、一字、二字ぐらいまで行けば、
全体として、どういう基調で
仕上がってくるかがわかります。
- 糸井
- ああ、なるほど。
- 石川
- もう一つ反故にしてしまうものがあります。
じつは、失敗だとしてはねている自分、
というのは過去のものです。
だけど、作品そのものの新しい世界は、
過去を超えて立ち上がってきます。
新しい世界が立ち上がってきたと、
うまく捕まえなければいけないのだけども、
それを見なれないものだから失敗だと思って、
捨てたものもあるでしょうね。
- 糸井
- もっと未来につながりたいのに、
今までの最大限が出てもおもしろくないな、
というような志の問題ですか。

- 石川
- 人間は絶えず変わっていくものです。
変わっていくものだし、変わっていかなかったら、
本人が気づかなくても確実に頽廃していきます。
徐々に自分に嫌気がさしてきますから、
絶えず新しいものを作っていかなきゃならない。
新しいものっていうのは、
異な顔立ちでやってきますから、
今まで待ち望んでいたものだというふうに
捕まえられりゃいいけども、
そうでない場合には、
あっ、失敗だと思って捨ててしまうこともある。
- 糸井
- 捨てる判断が間違っていたなんてことも、
あり得るんですね。
- 石川
- そう、それはあると思います。
- 糸井
- そう聞くと、よくわかりますね。
保留にしておくということも
ありますよね。
- 石川
- もちろん、それはありますね。
ある程度、ゆるやかな目で、
ちょっと置いておくものはありますね。
なんか気になるんですよ。
いろんなまずい所があるけど、
それがこれまで見えなかったものの
出現であったりする。
展覧会なんて、基本的にぼくは、
子別れの儀式だと思うんです。
- 糸井
- 子別れの儀式ですか。

- 石川
- 書いた時には、自分が生んだ
手ざわりが残っています。
まだちょっと、感情がつながっているわけですよ。
そこで一日、二日、置いておいて判断する。
そして、展覧会にぽんと出すと、
今度は自分が観客みたいな顔をして見ることになる。
そうすると客観的に見られる。
「えっ、お前、意外とやるじゃない」と
受け容れることにもなります。
- 糸井
- 過去の作品と、今の目は違うんですね。
- 石川
- やっぱり作品って可愛いから、
自分とへその緒がつながっている感覚ですね。
書いた時には、感情が残っているんです。
「失敗した」、「うまくいった」とかね、
「手元が狂った」とかね。
そういうことが作品にベタッと張り付いていて、
作品は独立しているはずなのに、
なかなか独立してくれないんです。
だから、自分から切り離して見られる展覧会は、
いい機会だと思いますね。
- 糸井
- 子離れは子離れで難しいんですね、親として。
違う良さが見えてくることは、当然あるでしょうね。
- 石川
- ぼくも今、展覧会を開催するのは、
非常に興奮しているんですよ。
おもしろいものになるんじゃないかと。
- 糸井
- 人に会うわけですからね。
いい時期に、いい企画でしたね。
- (つづきます)

▲「歎異抄No.18」