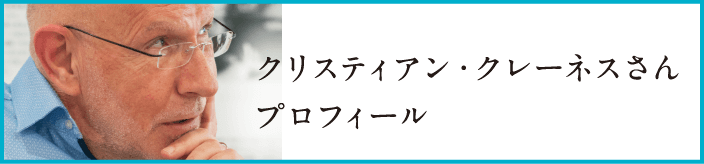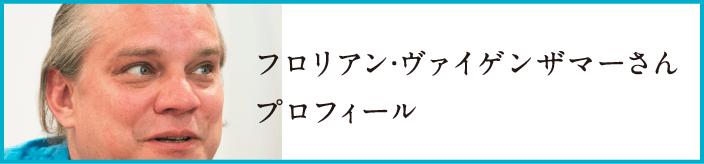03「人間とは、何か」ということを、
一生をかけて追求していきたい。
- ──
- 時代を映すインタビューというものが、
過去に、いくつかあったと思うんです。
- ヴァイゲンザマー
- ええ。
- クレーネス
- たくさん、ありますよね。
- ──
- 別に、大げさな意味でもないんですが、
時代や歴史に対して、
インタビューができることって何だと、
おふたりは、思われますか。
- クレーネス
- 非常に大事な観点だと思います。
今回のポムゼルさんのケースのように、
彼女の記憶自体が、
より大きな歴史に絡み合うような、
そういった記憶は、
歴史的、客観的な事実の記録と同様に
重要であるにもかかわらず、
放っておいたら、
彼女とともに、消えてしまいますよね。
- ──
- ええ。
- クレーネス
- そういう、どこにも残されない記憶を、
未来に対して「保存」すること。
そうすることによって、
将来、同じような出来事が起きたとき、
そのとき生きている人たちが、
何がしかの教訓を
引き出してくれるかもしれません。

- ──
- はい。
- クレーネス
- そういう役割が、まずあると思います。
たとえば「第二次世界大戦」のような、
途方もない災厄を生きて、
さまざまなことを見聞きしてきた人の、
記憶、思い出、気持ち‥‥
それらをインタビューというかたちで
残していくことは、
とっても重要なことだと思っています。
- ──
- 単なる事実でなく、その場にいた人の
「記憶、思い出、気持ち」って、
年表や教科書には載ってませんものね。
- クレーネス
- そうですね、まさにそのとおりです。
第二次世界大戦という大きな戦争が、
どんなきっかけで起こり、
どうやって終結していったのか‥‥。
- ──
- ええ。
- クレーネス
- そのような「冷たい情報」とはまた別に、
インタビュー、
つまり、誰かの口から語られた言葉には、
人間的な手触りがあります。
そこには、極めて個人的な受け止め方や、
主観的な判断、あるいは
脚色さえ混じっているかもしれませんが、
そういう「温度のある記憶」から、
学べることも、たくさんあると思います。
- ──
- ひとつ、ヴァイゲンザマーさんは、
インタビューの醍醐味って、
どんなところにあると思いますか。
- ヴァイゲンザマー
- 誰かをインタビューすることによって、
自分自身を知ることができること。

- ──
- ああ、なるほど。
- ヴァイゲンザマー
- たとえば‥‥自分がどれほど、
無意識のうちに偏見を抱いていたのか、
どういった問題意識を持っていたのか、
あるいは、
どういった問題に無頓着だったのか。
そういうことが、
誰かをインタビューすることを通じて、
見えてくることがあるんです。
- ──
- はい。
- ヴァイゲンザマー
- インタビュアーによって、
人それぞれだろうなとは思いますけど、
わたしにとっての
インタビューのいちばんの醍醐味って、
そういうところにありますね。
- ──
- わかります。誰かの話を聞いてるのに、
自分自身があぶり出されてくる感覚。
- ヴァイゲンザマー
- わたしたちは、どんな相手であろうと、
小さな子どもからであろうと、
何かを学ぶことができると思うんです。
どんな人も、
他の誰かの糧になる何かを持っている。
そして、その何かを、
自分自身を知るためのヒントにできる。
それが、
インタビューの醍醐味かなと思います。
- ──
- クレーネスさんは、いかがですか。
- クレーネス
- わたしが、インタビューをやっていて
つくづく思うのは、
「人間は感情の動物だ」ということ。
インタビューの最中に、
相手と激しく対立することもあってね。

- ──
- あるんですね。そういうことも。
- クレーネス
- あるいは、インタビュー相手の中に、
ふたつの対立する何かが、
激しくぶつかり合っているところを、
見ることもあります。
つまり、誰かをインタビューすると、
どちらの側からも、
ある種の強い感情が引き起こされる。
何らかの感情が、溢れてくるんです。
- ──
- ええ。ときには涙するくらい。
- クレーネス
- そのことが、おもしろいと思います。
自分の感情が他人の感情とふれあう、
感情の交感ともいうべきもの。
それって、
とても人間らしい営みじゃないかと、
わたしには、思えるんです。

- ──
- では最後に、少し大きな質問ですが、
「人間」とは何だと思いますか。
これまで、
たくさんの「人間」に話を聞いてきた、
おふたりにとって。
- ヴァイゲンザマー
- それは、とても重要なテーマですね。
インタビューという行為にとっても。
- ──
- そうですか。
- ヴァイゲンザマー
- だって我々は、
いわば、その答えを見つけるために、
インタビューを続けているから。

- ──
- ああ‥‥。
- ヴァイゲンザマー
- 答えは、まだ、見つかっていませんが、
インタビューを続けていけば、
人間とは何か、という問いの答えに、
一歩でも近づける‥‥
そう信じて、インタビューしています。
人間とは何か、という問いへの解答は、
一生をかけてでも、
追求していきたいと思っているんです。
- ──
- 自分も、インタビューを通じて
「人間って、どういうものなんだろう」
ということについての
自分なりの考えに、
いつかたどり着きたいと思っています。
- クレーネス
- 我々は人間がやっていることすべてに、
興味があるんですよね。
自分以外の他の人の日常生活や人生は、
なぜ、自分たちのそれと違うんだろう。
- ──
- ええ。
- クレーネス
- なぜ、こういう生活をしてるんだろう。
なぜ、こういうふうに
生きなければならなかったんだろう。

- ──
- そのことが知りたいんですね。
- ヴァイゲンザマー
- 知りたいです。
そして、幸運にも知ることができたら、
他の人にもぜひ知ってほしい。
- ──
- なるほど。
- ヴァイゲンザマー
- 時代や歴史という大きな事柄についても、
あるいは逆に、
名もなき人の人生の記憶についても、
知り得たことを、誰かに語りたいと思う。
- ──
- 大きくても、小さくても、等しく同様に。
- ヴァイゲンザマー
- それも、大げさな口ぶりじゃなく、
となりの席の友だちに、
「そういえば昨日、
こんなことがあったんだけどさ」
って、話しかけるような感じでね。

- ──
- センセーショナルな方法ではなく、
言葉を、ひとつひとつ積み上げるように。
- ヴァイゲンザマー
- そんなふうにできたらいいなと思います。
<終わります>
2018-06-20-WED
映画『ゲッベルスと私』、公開中です。

© 2016 BLACKBOX FILM & MEDIENPRODUKTION GMBH
モノクロ画面の中、在りし日のポムゼルさんは、
ナチス政権下の自らの生活を、
静かに、たんたんと、振り返ります。
大きな歴史の中の、半径数メートルの出来事を。
上司だったゲッベルスについても、
「見た目のいい人だった。
手もよく手入れされていた。
きっと毎日、爪のケアを頼んでいたのね」
と回想します。
映画のタイトルは「ゲッベルスと私」ですが、
ブルンヒルデ・ポムゼルという女性の人生を、
その100年以上に及ぶ人生を描いた、
より大きくて、ちいさな物語だと思いました。

© 2016 BLACKBOX FILM & MEDIENPRODUKTION GMBH
この映画は、有田浩介さんという「個人」が
配給しています。
たったひとりで映画を買い、劇場と交渉し、
宣伝し、配給している人は、
映画界広しといえども、めずらしいそうです。
今回、原稿のやり取りをする中で、
有田さんのくれたメールが、
映画に対して自分が感じたことと似ていたので、
そしてそれが、より的確に表現されていたので、
ご本人の了承を得た上で、紹介いたしますね。
「最初、この映画を見たとき、
ポムゼルさんは嘘をついていると思いました。
ポムゼルさんのインタビューの中に、
ちいさな矛盾を感じたのです。
同時に、そのことが、
映画のメッセージでないこともわかりました。
3回目を見終えたところで、
ポムゼルさんを通じて、
4人の監督が伝えようとしていることを、
うっすら感じることができました。
衝撃ではなく、静かな力強さ。
私がこの映画を買ったきっかけは、
それがすべてだったと、
インタビューを読みながら、振り返りました」


© 2016 BLACKBOX FILM & MEDIENPRODUKTION GMBH
東京・岩波ホールにて公開中。
ほか全国劇場で順次ロードショー。
くわしくは、公式ホームページでご確認ください。
有田さんの配給会社サニーフィルムのHPはこちら。