
![デヴィッド・ルヴォー対談 だから演劇はやめられない。 ──昔の日々と、今の日々。── ゲスト 宮沢りえ[役者と演出家編]/木内宏昌[演出家と劇作家編]](images/head_4.png)
![[演出家と劇作家編]その1 もうすべてを倒してやれ!](images/t_02.png)
| ルヴォー | 『ナイン(Nine)』からナイン・イヤーズですね。 ナイン・シンス・ナイン。 あれはもう9年前ですよ。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 『ナイン(Nine)』 1982年初演の、ブロードウェイ・ミュージカル。 フェリーニの映画『8 1/2(はっかにぶんのいち)』が ベースになっている。 ルヴォーさんが演出をしたのは、 2003年のブロードウェイ・リバイバルから、 そのときの主演がアントニオ・バンデラスさん。 その公演でトニー賞2部門を受賞 (さらに6部門にノミネート)している。 日本では2004年にルヴォーさんの演出で 日本語・日本人キャストで初演、 2005年の再演のときには「ほぼ日」でも特集を組んだ。 (そのときの主演は別所哲也さん。) 2009年にはダニエル・デイ=ルイス主演で映画化された。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
| 木内 | そんなに経つんですね。 |
| ── | これだけ経つと、 『ナイン』のことを知らない人もいます。 だから改めてルヴォーさんのことを ぼくたちは強く紹介したいなと思っているんです。 |
| ルヴォー | タノシミデス。 |
| 木内 | きょうはぼくが個人的に聞きたいことを たくさん聞いちゃおうと思ってるんです。 |
| ルヴォー | それが一番いいことですよ。 |
| 木内 | ルヴォーさん、初めて日本に来たとき、 どんなことを考えて来たんですか? |
| ルヴォー | まさに今日、初めてのロンドンから東京の フライトで乗った飛行機を思い出していました。 コンタクトがむずかしい国なんだろうなぁ、 もうはるか不可能の先にある、 遠い、秘密主義的で複雑な文化と 出会うんだろうなぁと思いながら来たんです。 つまり馴染みのない文化であるということを 楽しみに来ようと、 それを冒険と捕らえようと思って。 でも同時に、日本は、美しさを捕らえるイメージを 豊かに持ってる文化だという意識もありました。 着物とか、いろんな、そういう日本の美が溢れていて、 最高の美と出会うだろうという、 そういうつもりもあって‥‥。 そして、ぼくが思ったその日本は、 あくまで外向きの日本だったと気づく、 次の段階に進むのには時間がかかりました。 |
| 木内 | それはどのくらいかかりましたか? |
| ルヴォー | まだ頑張ってる! |
| 木内 | まだ(笑)。 |
| ルヴォー | tpt(シアタープロジェクト・東京)を作ったのが 初来日から4、5年経ってからでしたね。 そこから、ただ単純に 「西洋人の演出家が演出しに来る」 だけじゃなくなりました。 人とちゃんと出会うことができたのは、 そこからだったと思います。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ tpt(シアタープロジェクト・東京) 東京・隅田川左岸の「ベニサン・ピット」を拠点に ルヴォーさんと、演劇プロデューサーの門井均さんが 立ち上げた、現代演劇の実験プロジェクト。 初演作品はエミール・ゾラの『テレーズ・ラカン』。 ルヴォーさんは2006年までのあいだに22作品の演出を 手がけている。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
 |
|
| 木内 | ぼくが初めてベニサン・ピットで ルヴォーさんの演出作品を観たのは、 『あわれ彼女は娼婦』でした。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 『あわれ彼女は娼婦』 イギリスで1620年代に執筆された劇。 日本での初演は1970年の文学座。 tptでの公演は1993年、豊川悦司さんも出演した。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
| ルヴォー | そうなんだ。 |
| 木内 | それまでぼくの演劇活動は、 学生劇団からの延長線にあったんですね。 当時、ぼくたちの一番の成功例は、 野田秀樹さんの「劇団夢の遊眠社」でした。 学生劇団っていうのは自分たちがやってることが 一番おもしろいと思っているんですね。 世界一おもしろい。 で、自分たちより年上がやってることは、 みんな否定してかかりたい。 |
| ルヴォー | 当然です。それが本質的に最も重要な反応でしょ? そう信じてないとできない。 |
| 木内 | ところが、ぼくの劇団の衣装スタッフが、 ルヴォーさんの『テレーズ・ラカン』で 衣装を手伝うようになって、 「そうじゃないかもしれないよ」って。 そして『あわれ彼女は娼婦』を観に行き、 『背信』を観て。 (ルヴォー演出による伝説の3か月連続公演でした!) ぼくら学生劇団出身からすると、 違う世界にいた新劇の本格派女優に、 ぼくらの先輩のような小劇団出身の 俳優たちが挑んでました。 当時は、ほかではありえない共演でした。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 『テレーズ・ラカン』 1993年、ルヴォーさんがtptではじめて演出した 日本語作品。佐藤オリエさん、藤真利子さん、 堤真一さんなどが出演。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 『背信』 1993年、tptでのルヴォーさん3作目の演出作品。 今回の『昔の日々』と同じハロルド・ピンターの作。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
| ルヴォー | はい、はい、わかります。 |
| 木内 | 本番の舞台が終わった後に、 その先輩俳優と、森下の中華屋さんで、 いかにデヴィッドに屈服したかという話を‥‥。 |
| ルヴォー | 屈服(笑)。 |
| 木内 | したわけです。 「そのデヴィッド・ルヴォーっていう演出家は 何がすごいんだ?」という話になって、 スタッフも先輩俳優も言っていたのは、 「稽古のあいだずっと俳優たちを 気持ちよく演じさせるんだ」って。 その頃、どこか演劇を作る過程っていうのは、 いかに自分を追い詰め、苦労して、否定され‥‥。 |
| ルヴォー | 笑っちゃう(笑)。 わかります。スミマセン。 |
| 木内 | どれだけ痛い思いをするかだ、 みたいなところがあったんです。 そうすることでこそ、本番で輝くという。 「だけど、そうじゃないんだよね」って。 衝撃でした。 |
| ルヴォー | 大学時代は、自分も同じことを思ってましたよ。 白塗りとか、そういう前衛的なこともいっぱい。 「だからこそ、ぼくらの演劇は、 商業的なものではなくて、純粋なのだ」 と、信じてやってたんですね。 それをやることは大切なことだった。 制度に対して反撃しなかったら、 意味がないっていうところもあるから。 でも、そこでもっと重要なのはね、 体制に反対しつつ観客を獲得するにはどうするか。 学生っていうのは、やっぱり観念になっちゃう。 だけど、現実の世界って、観念なんか追いつけないほどに、 ラディカルなものを持っているんです。 それを学んだことが大きかったな。 |
| 木内 | その「ラディカル」って、 もうちょっと詳しく言うと‥‥? |
| ルヴォー | 「抜本からひっくり返す」ということ。 「革命的」っていう意味で使っています。 |
| 木内 | ひっくり返しちゃう? 抜本からなんですね。 |
| ルヴォー | そう、抜本からひっくり返すような革命性を持っている。 ぼくは、日本に来る頃までに 自分の中で確立していたことがあるんです。 それは、既成の演劇が使う「感情」というものの表現と、 「性」というものの表現が気にくわなかったということ。 若い演出家として、そういうスタンスでいたんです。 イギリスでもアメリカでもいいけれども、 劇評家が認め、一般大衆が認めた演劇とやらを観に行くと、 非常に狭い、きちんとしたまともなもので、 「つまらないな」と思っていたんですよ。 怒っていたと言ってもいいです。 けれどぼくは、自分で表現するには、 まだ、技術っていうものをほとんど持っていなかった。 舞台というものの作り方、見せ方を これから学んでいかなきゃいけなかった。 そんな自分にとって、 自分の傾向を決定づけたと言える作品は、 ユージン・オニールの作品でした。 「感情っていうのは、 これくらい大きく表現できるんだ、 このヤロー!」というくらいに、やったんです。 そのね、文芸的な演劇とやらをひっぱたきたかった。 爆弾を落としてやりたかった。 「はい、これ、合格」って丸を付けるみたいな、 そういう採点表みたいな見方しかしない 劇評家の姿勢にも腹を立てていたし。 その時ぼくは23歳くらいでしたから、 まだ、技術が優れていたわけでもなんでもなく、 言ってみれば荒削りです。 舞台としてそんなに美しくはなかっただろうし、 上手な俳優は出ているけれど、 整ってない、音ばっかり大きい和音を出していた。 ぼくの持っている既成の演劇っていうもののイメージは、 美しい旋律をみんなが静かに聴いている、 というものなんだけれど、 そこへ(テーブルの上を散らかして音を立てて) こういうのが来ちゃったわけです。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ユージン・オニール 20世紀はじめから中頃にかけて活躍したアメリカの劇作家。 「アメリカ近代演劇を築いた人」として知られる。 代表作に『カーディフを指して東へ』、 『地平線の彼方』(ピューリッツァ賞受賞)、 『皇帝ジョーンズ』『アナ・クリスティ』 『楡の木陰の欲望』などがある。 1936年にノーベル文学賞を受賞。 ルヴォーさんがはじめて演出したオニールの戯曲は 『日陰者に照る月』。 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
| 木内 | グチャグチャグチャ(笑)! |
 |
|
| ルヴォー | スミマセン。でも、そういうものが自分だと思う。 「もうすべてを倒してやれ」っていうのが、 自分の最初の衝動です。 それも観念ではなく、情熱だけで。 「ワーッとやっちゃった後で、理解すりゃいいや」 みたいな。先にやるだけやる、っていう。 「新聞とか劇場とかで言われている、 みんなが認めるよりも、物事ってもっとでかいよね」 っていうことだけはわかってたから、それだけをやった。 「演劇に関する俺の理論を観客にレクチャーする」 みたいな演劇ってあると思うけど、初めて演出をした時に、 「俺、何の理論も持ってない」っていうことに気が付いて。 「命っていうものの近くにだけいたい」 としか思っていなかったんですね。 |
| (つづきます!) | |
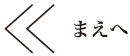 |
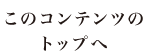 |
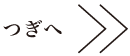 |